経済的残存耐用年数に関する問合せが増えている。背景には、建物の老朽化が進行するなかで、建築費の高騰による建替えの難しさがあり、既存建物をいかに長く活用できるかが重要な経営課題となっており、さらに建物を担保に融資している金融機関にとっては、今後どの程度の期間、経済的価値を保ちうるのかという判断が融資方針に直結するため、実態に即した経済的残存耐用年数によって建物を評価したいということと推察する。
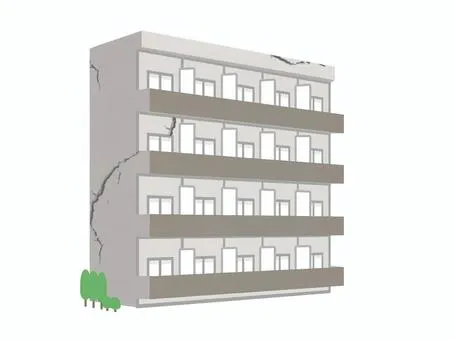
さて、ここで建物の耐用年数とは何だろうか。「建物が構造的な安全性を保ちながら、主要構造部(基礎・柱・梁・床・屋根など)が大規模な補修や改築なしで使用に耐えるとされる年数」これが建築学的な物理的耐用年数の定義となっている。RC造であれば60年、木造なら40年など構造別の年数が用いられている。一方、経済的耐用年数は、建物の構造別に定められた画一的な年数(たとえばRC造であれば50年、木造なら35年など)を基準として設定されることが多いため、物理的耐用年数よりも短く、建物ごとの個別性が十分に考慮されておらず、評価額や担保価値に対して現実との乖離が生じるリスクがある。経済的耐用年数は、本来、単なる躯体や設備の寿命ではなく、建物が経済的に機能しうる期間、すなわち収益性を持ち続ける期間を意味すべきである。たとえば、老朽化による賃料逓減、修繕更新費の増加などを踏まえて計算されたキャッシュフローに基づく考え方は、経済的実態に即した合理的な評価手法であるといえる。
「何年使えるか」ではなく、「いつまで収益を生み、価値を維持できるか」という問いに応えるアプローチである。経済的残存耐用年数の本来の定義に合致させるために、物理的な建物劣化の進行、地域市場の動向、将来収益の見通しといった複数の観点を統合的に分析するモデルの構築が不可欠である。これを実現するには、個々の建物の修繕履歴や、地域における賃料水準、市場性、キャッシュフローのシミュレーション結果など、広範な実証データの蓄積と活用が求められる。統計的手法による分析も有効であろう。従来の一律的な年数設定に代わり、実態と収益性を重視した柔軟かつ客観的な経済的残存耐用年数が求められている。こうした視点は、持続可能な建物管理の精度向上にも資するものであり、その社会的意義は大きいと考える。
株式会社不動産経営ジャーナル「週刊不動産経営」より転載(許諾済)

.webp)
.webp)
























